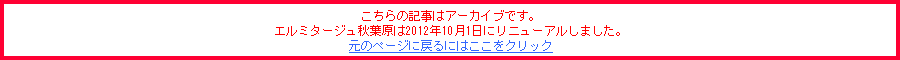編集部:
少し話はずれますが、USB3.0のコントローラーチップについて、GIGABYTE製マザーボードは比較的ハイエンドなモデルでルネサステクノロジ(旧NECエレクトロニクス)、ミドルからローエンドの製品でEtronを採用しているように見受けられます。このあたり理由はあるのでしょうか。
ビンセント氏:
 |
| Etron TechのUSB3.0コントローラーチップ |
|
|
結論から言うと特にはないですね。当初はルネサステクノロジ(旧NECエレクトロニクス)からしか供給されていなかったので、他に選択肢はありませんでした。最近ではEtronのような台湾メーカーのコントローラーもありますので、徐々に採用されているというのが実情です。
編集部:
パフォーマンスやコストに違いはあるのでしょうか?
ビンセント氏:
パフォーマンスについて違いはないはずです。コストについては多少の差はあると思いますが、それほど深刻なものではないと考えています。
|準備は順調。下半期にはBIOSからUEFIへの移行を目指す
編集部:
それでは、本日一番聞きたかったことをお伺いしていこうと思います。SandyBridge世代から、各社とも一斉に「BIOS」から「UEFI」に変更しました。ところがGIGABYTEだけといってもいいと思いますが、未だに「BIOS」です。3TB HDDへの対応等は独自にされているのは承知していますが、やはり気になります。
普段アキバを取材しているメディアの立場として感じるのは、「BIOS」の採用を理由に一部ユーザーさんの選択肢から外れているという印象を受けます。もし「UEFI」への移行予定があれば教えていただけますか?またはそもそも移行予定はないのでしょうか?
ビンセント氏:
正直に話すと、すでにGIGABYTEでは「UEFI」の準備はできています。現在も新製品開発毎に「レガシーBIOS」と「UEFI」2つを用意して、どちらもテストを行っています。
ただ両者をテストした結果、パフォーマンスを最大限に発揮できるのは、現時点で「レガシーBIOS」なのです。しかし今後もテストを重ねていき、「UEFI」で納得するパフォーマンスが出せると判断した場合、切り替えていく準備は整っています。具体的な時期としては下半期を考えています。
 |
| 特許出願中という「Touch BIOS」。キーボードやマウス、またはタッチスクリーンモニターを使用して直観的なシステム設定が可能とうたう |
|
|
編集部:
順調にいけば年末から年明けには移行が始まると。ちょうどSandy Bridge-Eの時期でしょうか。さて、そのパフォーマンスとは、いわゆるオーバークロック周りでしょうか。GIGABYTEの「BIOS」と言えば、昔から隠しメニューなども有名ですが。
ビンセント氏:
現在、我々の抱える開発チームは「Award BIOS」出身者で構成されています。隠しメニューについて「Award BIOS」は非常に強いんですね(笑)。ある意味こだわりもある。各デバイスとの相性も非常に出にくく、やはりご指摘の通りオーバークロックにも強い。例えば「AMD A75」搭載マザーボードですが、「BIOS」を採用することでオーバークロックパフォーマンスがとてもよい1枚に仕上がりました。オーバークロック周りはもちろん、パフォーマンスを低下させず、さらにリファレンスの「UEFI」ではないGIGABYTEオリジナルの「UEF」Iを開発し、ユーザーさんにお届けしたいと考えています。
編集部:
例えば、御社お得意の「DualBIOS」。BIOSとUEFIを入れちゃうなんてことは考えませんか?
 |
| GIGABYTEといえば「DualBIOS」。現在ではHybrid EFI Technologyとして3TB HDDにも対応。ブート機能をサポートする |
|
|
ビンセント氏:
考えないわけではありません。ただ「DualBIOS」本来の目的であるリカバリー機能が「BIOS」と「UEFI」で上手く連動してくれるのかテストを重ねる必要がある。ユーザーに対して混乱を招かないかという懸念もあります。 |