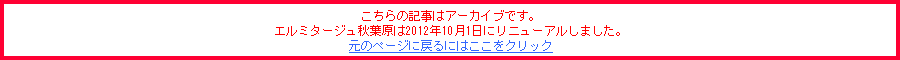|
|
| |
|DynaLoopベアリングを採用する120mmデュアルファン
「V6GT」はデフォルトで2基の120mmファンが搭載されている。近頃リリースされるCPUクーラーの多くはシングルファン仕様で、オーバークロッカーやハイスペック構成での運用を考えて、もう1基のファンは任意搭載できるという手法が取られている。
これまでお届けしたテストでも、吸排気のスピードが向上するデュアルファン仕様にする事で、冷却能力が向上する事が分かっているが、「V6GT」ではなぜ敢えてデュアル仕様を選択したのだろうか。ここからは想像だが、デフォルトからシングルファン仕様にする事で冷却能力に不安があったため、、、という事ではもちろん無く、前述の“Double-V”の効果を最大限発揮させるために、それ相応のエアフローが必要だったからではないだろうか。もう一歩踏み込むと、静音性が損なわれる事を承知の上で、高冷却にシフトしたモデルが「V6GT」とも言える。
 |
 |
| スクリューレスで固定されているファンカバーのツメをこじ開けると、簡単にファンが着脱可能。CPUクーラーの味付けを変えたいユーザーへの配慮か? |
 |
 |
| 搭載される2基のファンは同スペック。型番は「FA12025H12LPD」と「A12025-22CB-6AP-C1」の2種類が記載されていた |
ヒートシンク接触面にのみ用意された振動防止用ゴム。これが四隅に貼られている |
 |
120×120×25mmファンは“DynaLoopベアリング”と呼ばれる軸受け構造を採用。PWM制御の回転数は800〜2,200rpmと可変幅が広い印象。なお騒音値は15〜38dBA、風量は34.02〜93.74CFM、静圧は0.43〜3.30mmH2O |
|発光ギミックをチェックしておく
「V6GT」はCPUクーラー本来の仕事である冷却だけでなく、エンジンフード状カバーにオイルキャップ風のLEDカラー切り替えスイッチを搭載させ、発光を楽しむというギミックを装備している。この手の“茶目っ気”は賛否両論の部類に入るが、消灯(OFF)も選択できる事で不要なユーザーへの配慮も見て取れる。
 |
 |
| オイルキャップ風ロゴ入りボタンは、LEDカラー切り替え用。スイッチ自体はやや頼りない、いわゆる“ペコペコスイッチ”。とは言え、サイドパネルを閉じてしまえば常時切り替える事ができるワケでもなく、余計なコストが掛かるくらいならば不要という声もあるかもしれない |
 |
 |
 |
 |
| LED発光ギミックと見ても仕方がないカバー裏面の基板部。作りとしては非常に簡単で、電気の知識があれば自作可能なレベル |
|マザーボード搭載手順をチェックしてみる
次にマザーボードへの取り付け方法を、同梱のリテンションキットと共に見て行きたい。
CoolerMasterのCPUクーラーは、エントリークラス(3,000円台程度)のモデルと、アッパークラス(8,000円以上)のモデルでは、搭載方法が違う。もちろん自重が1kgに近い製品をプッシュピンで支えようというのは無謀であるため、「V6GT」ではバックプレートを使ったネジ留め式が採用され、脱落防止およびCPUコアとの確実な接触、さらにマザーボードの歪みを軽減する事ができる。
■リテンションキットとネジ類
 |
 |
| 別箱に入れられたリテンションキット一式 |
こちらはAMD Socket AM3/AM2+/AM2用の台座とCPUクーラー本体を固定するバネネジ付きのアーム |
 |
 |
| Intel系のバックプレートと台座 |
バックプレートは絶縁シートが貼られている |
 |
 |
| LGA775/1366/1156は、事前にネジ穴をずらしておく必要がある |
ジッパー袋に入れられたグリスとネジ類。六角ネジを固定する専用レンチが同梱される他、+ドライバでも固定できるようにヘッドが同梱されている。これは「風神匠」あたりからよく採用されている方式 |
■トラブルのオマケ付き。LGA 1156で実際に搭載してみる
次にリテンションキットを使って、実際に「V6GT」をマザーボードに搭載させて行くが、ここでお断りをしておかなければならない自体に陥った。
「一点突破 CPUクーラー編」のテストマザーは、EVGA「141-LF-E658-KR」(P55 Express/ATX)だが、CPUクーラー本体を搭載させるための台座を組み込んでみたところ、なんとVRM+チップ用に搭載されているCPUソケット外周のヒートシンクに物理的干渉を起こし、正しいエアフロー方向では装着ができなくなってしまった。
確かにハイエンド向けマザーボードだけあって、豪華なヒートシンク群ではあるものの、「V6GT」のヒートパイプの曲げ方向が邪魔をするとは思いもよらない。どちらが悪いかについての議論は避けるが、事前にチェックできない部分とはいえ、店頭で店員に相談してみる事を念のためオススメしておきたい。
 |
 |
| まずは台座を作る。Intel共通のバックプレートをマザーボード背面に合わせ、表面からリテンション2本をネジ固定。リテンションの方向には注意が必要で、この向きによってエアフロー方向の縦横が決まる。CPUクーラー本体を仮合わせした方が安全。ここまではよかった、、、 |
 |
 |
| ファンを事前に取り外し、ヒートシンクを載せる。なおここから旧テストマザー、GIGABYTE「P55A-UD3」にチェンジ |
ヒートシンクを台座に固定する金具は、ベース部上に突き出た2つの突起と固定金具の穴を合わせ、両端のバネネジで締め付ける |
 |
 |
| 平均的にテンションを掛けて、台座に固定。Intel、AMD問わず2点留め式。なおファンを事前に外しておかないと、ネジを締め付ける事ができない |
 |
 |
| ファンを元に戻せばマザーボードへの搭載は完了。4pin PWMコネクタをマザーボードに挿せば、あとは動作させるのみ。なおLED発光用4pinコネクタもお忘れ無く |
|大型サイドフローにおけるメモリスロットとの物理的干渉問題
これまでにテストしたCPUクーラーの多くはメモリスロットをフルに活用できない、または背の高いヒートスプレッダが装着されたメモリが一部スロットでは使えないという事態に見舞われた。特にサイドフロー型CPUクーラーの大型化により、今や珍しい事では無くなっているが「V6GT」は果たしてどうか。
マザーボードへの装着が完了したところで、メモリスロットとの位置関係をチェックしておこう。
 |
| 極一般的な高さの製品を選べば、4スロット全てにメモリを搭載させる事ができる。ただしCPUクーラー搭載後ではなく搭載前に挿しておかなければならない |
|
画像でも分かる通り、「V6GT」の場合、通常サイズのメモリであれば、CPU側のメモリスロットも使える事が分かった。これは「V6GT」の放熱フィンと受熱ベース間のヒートパイプが一般的なCPUクーラーに比べ広く(高く)取られているためで、ある程度メモリスロットが犠牲にならないように配慮されている事が分かった。CPUクーラー搭載後は取り付けるためのスペースが無くなるため、事前にメモリを装着しておく必要はあるものの、メモリ自体の価格が手頃な上、64bit OS環境での使用を考えると、やはりメモリスロットはすべて使える事が望ましい。
一方で、ハイエンド向けCPUクーラーを謳いつつ、大型ヒートスプレッダモデルやメモリ冷却ファンが搭載できないケースはなかなか理解し難く、CPUクーラーとメモリスロットの関係は、マザーボードのレイアウトを含め、改良の余地がある部分と言えるだろう。
以上を踏まえ、現状CPUクーラー側に望むのは、外形寸法の明記だけでなく、CPUを中心にどのくらいのスペースを要するのかをパッケージにはっきり明記すべきではないだろうか。特に「V6GT」のように比較的価格が高いモデルはなおさらで、いざ搭載という段になってからのショックは計り知れない。
| CoolerMaster“V3兄弟”の最新作「V6GT」の外観チェックおよび搭載手順を確認した後は、いよいよ冷却性能のテストを行ってみたい。強力なエアフローを生み出すデュアルファン仕様のパフォーマンスや如何に。 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
| |
|
|